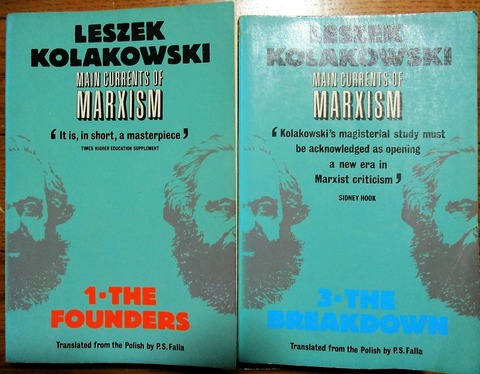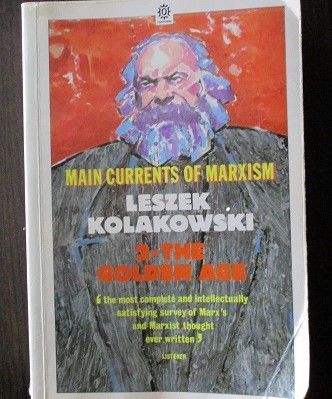リチャード・パイプス(Richard Pipes)・ロシア革命/1899-1919 (1990年)。総頁数946、注記・索引等を除く本文頁p.842.まで。
第11章・十月のクー。試訳のつづき。
----
第11節・ボルシェヴィキが臨時政府打倒を宣言①。
(1)ボルシェヴィキ・クーの最終段階は、10月24日、火曜日の朝に進行していた。それは、軍事幕僚たちが政府によって前夜に命じられた熱の入らない手段を履行したあとだった。
10月24日の早い時間に、<ユンカー(iunkers)>が戦略的重要地点を護衛する義務を受け持った。
二または三の部隊が、冬宮の防衛のために派遣された。そこで彼らは、140人の志願者から成るいわゆる女性決死部隊(Women's Death Battalion)、いくつかのコサック、自転車部隊、将校に指揮された義肢の、および若干の銃砲の破片が体内にある、40人の戦争傷病者の兵団と合流した。
驚くべきことに、一発の銃砲も用いられなかった。
<ユンカー>は、<Rabochiipof>(<元プラウダ>)と<兵士>の印刷所を閉鎖した。 スモルニュイとの電話線は、切断された。
親ボルシェヴィキの兵士や労働者が首都中心部に入るのを阻止するため、ネヴァ河(Neva)に架かる橋を上げよとの命令が、発せられた。
政府軍事幕僚は、連隊に対して軍事革命委員会の指示を受けることを禁じた。
また、実際の効果はなかったが、軍事革命委員会のコミサールを逮捕せよとも命じた。(187)//
(2)こうした準備によって、危機の雰囲気が生まれた。
その日、ほとんどの事務所は午後2時半までに閉じられ、人々は家へと急いで帰って、街頭は空になった。
これは、ボルシェヴィキが待ち望んでいた「反革命」の合図だった。
ボルシェヴィキはまず、彼らの二つの新聞を復刊させた。午前11時までに、これを達成した。
つぎに、中央電信電話局とロシア電信庁を奪取すべく、軍事革命委員会は武装分団を派遣した。
スモルニュイからの電話線は再びつながった。
このように、クーの最も早い目標は、情報と通信線の中心地だった。//
(3)その日午後に行われた唯一の実力行使(violence)は、軍事革命委員会の部隊がネヴァ河を横切る橋梁を下げさせたことだった。//
(4)蜂起がこの最後で決定的な段階に至っているとき、軍事革命委員会は10月24日夕方、風聞にもかかわらず、反乱をしているのではなく、たんに「ペトログラード連隊と民主主義」を反革命から防衛する行動をしている、との声明文を発した。(188)//
(5)考えられ得ることしてはこの虚偽情報の影響を受けて、全く連絡をとっていなかったに違いないレーニンは、同僚たちに実際に行っていることをさせるべく、絶望的な覚え書を書いた。//
「私はこの文章を(10月)24日夕方に書いている。状況はきわめて深刻だ。
今や本当に、ますます明らかになっている。蜂起を遅らせるのは、死に等しい。//
ある限りの最大の力を使って、同志たちに訴えたい。全てがいま、危機一髪の状態だ。どの集会に(ソヴィエト大会であっても)諮っても回答されない問題に直面している。答えられるのは、人民、大衆、武装した大衆の闘いだけだ。//
コルニロフ主義者のブルジョア的圧力、Verkhovskii の解任は、待つことはできない、ということを示す。
ともかく何であれ、必要だ。この夕方、この夜に、政府人員を拘束すること、<ユンカー>を武装解除する(抵抗があれば打ち負かす)こと、…<略>。
誰が、権力を奪うべきなのか?
これは、今すぐには重要でない。軍事革命委員会に権力を、または「何らかの他の装置」を奪取させよ。…<略>//
権力掌握こそが、蜂起の任務だ。その政治的目標は、権力を奪取した後で初めて明らかになるだろう。//
10月25日の不確実な票決を待つのは、地獄か形式主義だ。
人民には、投票によってではなく実力行使でもってその問題を解決する権利と義務がある。…<略>」(*)//
--------
(*) レーニン, <PSS>XXXIV, p.435-6. Verkhovskii は、ロシアは中央諸国と即時講和をすべきだと閣僚会議で主張して、その前日(10月23日)にその職を解任されていた。<SV>No.10, 1921年6月19日, p.8.
--------
(6)レーニンは、その夜おそく、スモルニュイにやって来た。
彼は完全に変装していて、包帯を巻いた顔からして歯医者の患者のように見えた。
途中で政府の巡視隊にほとんど逮捕されるところだったが、酔っ払っているふりをして免れた。
スモルニュイでは、背後の部屋の一つにいて、最も親しい仲間たちだけが近づけるようにして、姿を消したままでいた。
トロツキーは、こう想起する。レーニンは、軍事幕僚との間に進行中の交渉について聞いて懸念を覚えたが、この対話は見せかけ(a feint)だと理解すると、ただちに愉快に微笑んだ。//
レーニンは「おう、それはよい(goo-oo-d)」と陽気に強い声で言って、緊張して手を擦りながら、部屋の中を行ったり来たりしていた。
「それは、とても(verr-rr-ry)よい」。
レーニンは軍事的な策謀を好んだ。敵を欺くこと、敵を馬鹿にすること-何と愉快な仕事だ!(189)//
レーニンはその夜を床の上でゆっくりと過ごした。その間に、ポドヴォイスキー、アントノフ=オフセエンコ、およびトロツキーの全幅的指揮下にある彼の友人のG. I. Chudnovskii が、作戦行動を司令した。//
(7)その夜(10月24日-25日)、ボルシェヴィキはピケを張るという単純な方法で、戦略上重要な目標地点の全てを系統的に奪い取った。
Malaparte が論述したように、これは現代の模範的なクー・デタだった。
<ユンカー>護衛団は、家に帰れと言われた。そして自発的に撤退するか、または武装解除された。
こうして、闇夜に紛れて、一つずつ、鉄道駅、郵便局、中心電話局、銀行、そして橋梁が、ボルシェヴィキの支配のもとに置かれた。
抵抗に遭遇することはなく、一発の銃火も撃たれなかった。
ボルシェヴィキは、想像し得る最もさりげない方法でエンジニア宮を奪取した。
「彼らは入ってきて、幕僚たちが立ち上がって去っていった座席を占めた。かくして、幕僚本部は奪取された。」(190)
(8)ボルシェヴィキは、中央電信電話交換局で冬宮からの電話線を切断した。しかし、登録されていなかった二つの線を見逃した。
この二つの線を使って、Malachite 室に集まっていた大臣たちは外部との接触を維持した。
ケレンスキーは、公的な声明では自信を漂わせてはいたものの、ある目撃者によると、「苦悩と抑制した恐怖」を隠して半分閉じた眼で、虚ろを見つめて誰も視ておらず、老けて疲れているように見えた。(191)
午後9時、T・ダン(Theodore Dan)とAbraham Gots が率いるソヴェト代表が現れて、「革命的」軍事参謀の影響によってボルシェヴィキの脅威を過大評価している、と大臣たちに告げた。
ケレンスキーは、彼らを閉め出した。(192)
その夜にケレンスキーはついに、前線の司令官たちに連絡をし、救援を求めた。
しかし、無駄だった。誰も求めに応じなかった。
10月25日午前9時、ケレンスキーは、セルビア将校に変装し、アメリカ合衆国大使館から借りた車で冬宮を抜け出した。その車はアメリカの旗を立て、助けを求めて前線へと走った。
(9)その頃までに、冬宮は、政府の手に残された唯一の建造物だった。
レーニンが執拗に主張したのは、第二回ソヴェト大会が正式に開会して臨時政府を排斥する前に、大臣たちは拘束されなければならない、ということだった。
しかし、ボルシェヴィキの軍組織はその任務を果たすのに適切ではなかった。
彼らボルシェヴィキ部隊は主張はしたけれども、敢えて銃砲を放とうとする者たちがいなかった。
4万5000人いるとされた赤衛隊(Red Guards)とペトログラード守備連隊内部の数万の支持者たちは、どこにも現れなかった。
冬宮に対する不本意な攻撃が、明け方に始まった。しかし、最初の射撃の音を聞いて、攻撃者たちは退却した。
(10)苛立ちを燃え上がらせ、前線の兵団による介入を怖れて、レーニンは、もう待たない、と決断した。
午前8時から9時までの間に、彼は、ボルシェヴィキの作戦指揮室に入った。
最初は誰も、彼が何者なのか分からなかった。
ボンチ=ブリュエヴィチ(Bonch-Bruevich)は、彼がレーニンだと認識して、嬉しさが爆発した。「ウラジミル・イリイチ、我が父だ。きみだとは気づかなかった」と叫びながら、レーニンを抱擁した。(193)
レーニンは座って、軍事革命委員会の名前で臨時政府が打倒されたことを宣言する文書を起草した。
プレスに(10月25日)午前10時に発表された文章は、つぎのとおりだった。
「ロシアの市民諸君!
臨時政府は打倒された。
政府の権能は、ペトログラードのプロレタリアートと守備連隊の頂点に位置する、ペトログラード労働者・兵士代表ソヴェト、軍事革命委員会の手に移った。
人民が目ざして闘うべき任務-民主主義的講和の即時提案、土地にかかる地主的所有制の廃絶、生産に対する労働者による統制、ソヴェト政権の確立-、これらの任務の遂行は保障された。
労働者、兵士および農民の革命に栄光あれ!
ペトログラード労働者・兵士代表ソヴェトの軍事革命委員会。」(*)
--------
(*) <Dekrety>I, p.1-2. ケレンスキーの妻は拘束され、この宣言書を破ったとしてつぎの日の48時間留置された。A. L. Fraiman, <<略>>(Leningrad, 1969), p.157.
--------
(187) <Revoliutsiia>V, p.164, p.263-4.
(188) <SD>No.193(1917年10月26日), p.1.
(189) トロツキー, <レーニン>p.74.
(190) Maliantovich, <Boyle>No.12(1918年)所収, p.114.
(191) 同上, p.115.
(192) Melgunov,<Kak bol'sheviki>p.84-p.85.; A・ケレンスキー,<ロシアと歴史の転換点>(New York, 1965), p.435-6.
(193) S. Uranov, <PR>No.10/33(1924年), p.277.
-----
②へとつづく。
第11章・十月のクー。試訳のつづき。
----
第11節・ボルシェヴィキが臨時政府打倒を宣言①。
(1)ボルシェヴィキ・クーの最終段階は、10月24日、火曜日の朝に進行していた。それは、軍事幕僚たちが政府によって前夜に命じられた熱の入らない手段を履行したあとだった。
10月24日の早い時間に、<ユンカー(iunkers)>が戦略的重要地点を護衛する義務を受け持った。
二または三の部隊が、冬宮の防衛のために派遣された。そこで彼らは、140人の志願者から成るいわゆる女性決死部隊(Women's Death Battalion)、いくつかのコサック、自転車部隊、将校に指揮された義肢の、および若干の銃砲の破片が体内にある、40人の戦争傷病者の兵団と合流した。
驚くべきことに、一発の銃砲も用いられなかった。
<ユンカー>は、<Rabochiipof>(<元プラウダ>)と<兵士>の印刷所を閉鎖した。 スモルニュイとの電話線は、切断された。
親ボルシェヴィキの兵士や労働者が首都中心部に入るのを阻止するため、ネヴァ河(Neva)に架かる橋を上げよとの命令が、発せられた。
政府軍事幕僚は、連隊に対して軍事革命委員会の指示を受けることを禁じた。
また、実際の効果はなかったが、軍事革命委員会のコミサールを逮捕せよとも命じた。(187)//
(2)こうした準備によって、危機の雰囲気が生まれた。
その日、ほとんどの事務所は午後2時半までに閉じられ、人々は家へと急いで帰って、街頭は空になった。
これは、ボルシェヴィキが待ち望んでいた「反革命」の合図だった。
ボルシェヴィキはまず、彼らの二つの新聞を復刊させた。午前11時までに、これを達成した。
つぎに、中央電信電話局とロシア電信庁を奪取すべく、軍事革命委員会は武装分団を派遣した。
スモルニュイからの電話線は再びつながった。
このように、クーの最も早い目標は、情報と通信線の中心地だった。//
(3)その日午後に行われた唯一の実力行使(violence)は、軍事革命委員会の部隊がネヴァ河を横切る橋梁を下げさせたことだった。//
(4)蜂起がこの最後で決定的な段階に至っているとき、軍事革命委員会は10月24日夕方、風聞にもかかわらず、反乱をしているのではなく、たんに「ペトログラード連隊と民主主義」を反革命から防衛する行動をしている、との声明文を発した。(188)//
(5)考えられ得ることしてはこの虚偽情報の影響を受けて、全く連絡をとっていなかったに違いないレーニンは、同僚たちに実際に行っていることをさせるべく、絶望的な覚え書を書いた。//
「私はこの文章を(10月)24日夕方に書いている。状況はきわめて深刻だ。
今や本当に、ますます明らかになっている。蜂起を遅らせるのは、死に等しい。//
ある限りの最大の力を使って、同志たちに訴えたい。全てがいま、危機一髪の状態だ。どの集会に(ソヴィエト大会であっても)諮っても回答されない問題に直面している。答えられるのは、人民、大衆、武装した大衆の闘いだけだ。//
コルニロフ主義者のブルジョア的圧力、Verkhovskii の解任は、待つことはできない、ということを示す。
ともかく何であれ、必要だ。この夕方、この夜に、政府人員を拘束すること、<ユンカー>を武装解除する(抵抗があれば打ち負かす)こと、…<略>。
誰が、権力を奪うべきなのか?
これは、今すぐには重要でない。軍事革命委員会に権力を、または「何らかの他の装置」を奪取させよ。…<略>//
権力掌握こそが、蜂起の任務だ。その政治的目標は、権力を奪取した後で初めて明らかになるだろう。//
10月25日の不確実な票決を待つのは、地獄か形式主義だ。
人民には、投票によってではなく実力行使でもってその問題を解決する権利と義務がある。…<略>」(*)//
--------
(*) レーニン, <PSS>XXXIV, p.435-6. Verkhovskii は、ロシアは中央諸国と即時講和をすべきだと閣僚会議で主張して、その前日(10月23日)にその職を解任されていた。<SV>No.10, 1921年6月19日, p.8.
--------
(6)レーニンは、その夜おそく、スモルニュイにやって来た。
彼は完全に変装していて、包帯を巻いた顔からして歯医者の患者のように見えた。
途中で政府の巡視隊にほとんど逮捕されるところだったが、酔っ払っているふりをして免れた。
スモルニュイでは、背後の部屋の一つにいて、最も親しい仲間たちだけが近づけるようにして、姿を消したままでいた。
トロツキーは、こう想起する。レーニンは、軍事幕僚との間に進行中の交渉について聞いて懸念を覚えたが、この対話は見せかけ(a feint)だと理解すると、ただちに愉快に微笑んだ。//
レーニンは「おう、それはよい(goo-oo-d)」と陽気に強い声で言って、緊張して手を擦りながら、部屋の中を行ったり来たりしていた。
「それは、とても(verr-rr-ry)よい」。
レーニンは軍事的な策謀を好んだ。敵を欺くこと、敵を馬鹿にすること-何と愉快な仕事だ!(189)//
レーニンはその夜を床の上でゆっくりと過ごした。その間に、ポドヴォイスキー、アントノフ=オフセエンコ、およびトロツキーの全幅的指揮下にある彼の友人のG. I. Chudnovskii が、作戦行動を司令した。//
(7)その夜(10月24日-25日)、ボルシェヴィキはピケを張るという単純な方法で、戦略上重要な目標地点の全てを系統的に奪い取った。
Malaparte が論述したように、これは現代の模範的なクー・デタだった。
<ユンカー>護衛団は、家に帰れと言われた。そして自発的に撤退するか、または武装解除された。
こうして、闇夜に紛れて、一つずつ、鉄道駅、郵便局、中心電話局、銀行、そして橋梁が、ボルシェヴィキの支配のもとに置かれた。
抵抗に遭遇することはなく、一発の銃火も撃たれなかった。
ボルシェヴィキは、想像し得る最もさりげない方法でエンジニア宮を奪取した。
「彼らは入ってきて、幕僚たちが立ち上がって去っていった座席を占めた。かくして、幕僚本部は奪取された。」(190)
(8)ボルシェヴィキは、中央電信電話交換局で冬宮からの電話線を切断した。しかし、登録されていなかった二つの線を見逃した。
この二つの線を使って、Malachite 室に集まっていた大臣たちは外部との接触を維持した。
ケレンスキーは、公的な声明では自信を漂わせてはいたものの、ある目撃者によると、「苦悩と抑制した恐怖」を隠して半分閉じた眼で、虚ろを見つめて誰も視ておらず、老けて疲れているように見えた。(191)
午後9時、T・ダン(Theodore Dan)とAbraham Gots が率いるソヴェト代表が現れて、「革命的」軍事参謀の影響によってボルシェヴィキの脅威を過大評価している、と大臣たちに告げた。
ケレンスキーは、彼らを閉め出した。(192)
その夜にケレンスキーはついに、前線の司令官たちに連絡をし、救援を求めた。
しかし、無駄だった。誰も求めに応じなかった。
10月25日午前9時、ケレンスキーは、セルビア将校に変装し、アメリカ合衆国大使館から借りた車で冬宮を抜け出した。その車はアメリカの旗を立て、助けを求めて前線へと走った。
(9)その頃までに、冬宮は、政府の手に残された唯一の建造物だった。
レーニンが執拗に主張したのは、第二回ソヴェト大会が正式に開会して臨時政府を排斥する前に、大臣たちは拘束されなければならない、ということだった。
しかし、ボルシェヴィキの軍組織はその任務を果たすのに適切ではなかった。
彼らボルシェヴィキ部隊は主張はしたけれども、敢えて銃砲を放とうとする者たちがいなかった。
4万5000人いるとされた赤衛隊(Red Guards)とペトログラード守備連隊内部の数万の支持者たちは、どこにも現れなかった。
冬宮に対する不本意な攻撃が、明け方に始まった。しかし、最初の射撃の音を聞いて、攻撃者たちは退却した。
(10)苛立ちを燃え上がらせ、前線の兵団による介入を怖れて、レーニンは、もう待たない、と決断した。
午前8時から9時までの間に、彼は、ボルシェヴィキの作戦指揮室に入った。
最初は誰も、彼が何者なのか分からなかった。
ボンチ=ブリュエヴィチ(Bonch-Bruevich)は、彼がレーニンだと認識して、嬉しさが爆発した。「ウラジミル・イリイチ、我が父だ。きみだとは気づかなかった」と叫びながら、レーニンを抱擁した。(193)
レーニンは座って、軍事革命委員会の名前で臨時政府が打倒されたことを宣言する文書を起草した。
プレスに(10月25日)午前10時に発表された文章は、つぎのとおりだった。
「ロシアの市民諸君!
臨時政府は打倒された。
政府の権能は、ペトログラードのプロレタリアートと守備連隊の頂点に位置する、ペトログラード労働者・兵士代表ソヴェト、軍事革命委員会の手に移った。
人民が目ざして闘うべき任務-民主主義的講和の即時提案、土地にかかる地主的所有制の廃絶、生産に対する労働者による統制、ソヴェト政権の確立-、これらの任務の遂行は保障された。
労働者、兵士および農民の革命に栄光あれ!
ペトログラード労働者・兵士代表ソヴェトの軍事革命委員会。」(*)
--------
(*) <Dekrety>I, p.1-2. ケレンスキーの妻は拘束され、この宣言書を破ったとしてつぎの日の48時間留置された。A. L. Fraiman, <<略>>(Leningrad, 1969), p.157.
--------
(187) <Revoliutsiia>V, p.164, p.263-4.
(188) <SD>No.193(1917年10月26日), p.1.
(189) トロツキー, <レーニン>p.74.
(190) Maliantovich, <Boyle>No.12(1918年)所収, p.114.
(191) 同上, p.115.
(192) Melgunov,<Kak bol'sheviki>p.84-p.85.; A・ケレンスキー,<ロシアと歴史の転換点>(New York, 1965), p.435-6.
(193) S. Uranov, <PR>No.10/33(1924年), p.277.
-----
②へとつづく。