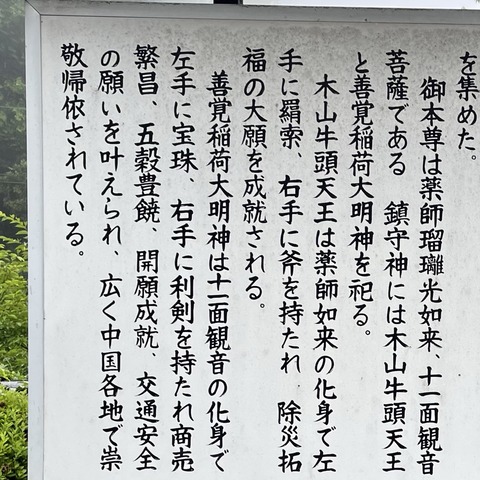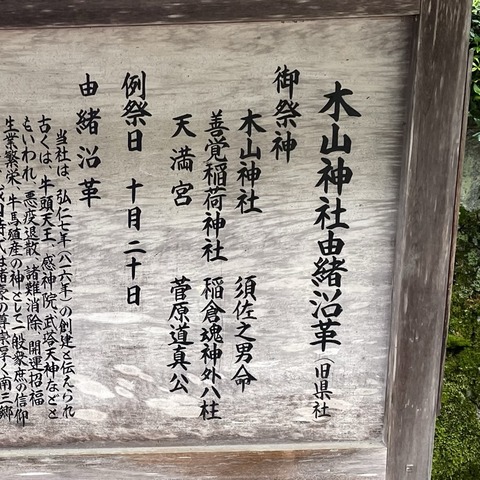①宇宙一②地球—③生物(生命体)—④遺伝子・分子—⑤素粒子。
--------
「細胞」は種々に分類されるのだろうが、つぎの二分が、まずは関心を引く。
第一に、「体細胞」と「生殖細胞」の区別。後者は精子、卵子、初期胚など。
精子・卵子は圧倒的多数の「体細胞」と違って減数分裂により生まれ、23本の「染色体」しかもたない。そんなことよりも、つぎの重要な違いをゲノム編集に関係して、秋月は知った。
すなわち、「体細胞」はゲノム編集の対象にすでになっている。換言すると、〈クリスパ・キャス9〉という「遺伝子」改変・「ゲノム」編集の方法がすでに適用されているのは、「体細胞」だ。一方、「生殖細胞」のゲノム編集については論議があり、大勢的な一致はない。但し、中国人研究者が(アメリカ留学で得た知識・技術を発展させて)中国で初期胚をゲノム編集し、それを女性に移植し、その女性は双子の女の子を出産した「事実」がある、とされる。
前者のゲノム編集の影響・効果は一世代に限定される。致命的疾患を発現させているような「体細胞」内の遺伝子が改変されても、その改変(・ゲノム編集)は次世代に影響を与えない。一方、遺伝子が改変された「生殖細胞」はその子どもの「生殖細胞」(女性だと卵子)に継承される。
--------
第二に、「再生系細胞」と「非再生系細胞」の区別。
前者・「再生系細胞」は、増殖したり、分化したりなどをする。新しい「細胞」に<再生>しうる。
後者・「非再生系細胞」は、増殖・分化しない。ヒトの場合、初期胚・胎児は増殖と分化を繰り返して「成長」するが、母体から離れるとき(新生児となるとき)以降は、心臓を拍動させる「心筋」細胞と脳内の「神経」細胞(ニューロン)は、もはや増殖することがない、とされる。
心筋梗塞や脳梗塞によって「壊死」した「心筋細胞」や「神経細胞」はもはや<再生>することがない。なお、例外は全くない、のではない、とされる。
この区別に表向きは隠されているようでもある重要な意味は、ヒト、つまり人類、人間の「細胞」や個体の「死」ないし「死に方」と密接な関係があることだ。
--------
「再生系細胞」が増殖するとは一つの細胞から二つの、そして四つの、…10回で1024個の同一の細胞が生まれることだ(限界まで増殖はつづく)。かつまた、元の、増殖前の細胞が「死ぬ」ことも意味している。
「分化」の場合も同じ。異なる細胞に「分化」する前の元の細胞は「死ぬ」。
上で「増殖したり、分化したりなどをする」と「など」を挿入したのは「死ぬ」こともあるからだ。
ここで「死」という言葉、概念を使うのは紛らわしいかもしれない。あくまでも「細胞の死」であって、通常は「死」の意味で用いられているだろう「個体の死」ではないからだ。その意味では、「消滅」の方がよいだろうか。だが、生命体の基本的単位である「細胞」についても「死」を語って奇妙ではないし、逆に、「個体の死」もまた、「個体の消滅」だ。
「細胞の死」またはその仕組みのことを<アポトーシス>と言うことがある(下掲書によると1972年に初めて提唱された)。
そして、この現象または仕組みはヒトを含む多細胞生物にもともと内在しているものとされる。「プログラム化された」死であり、「遺伝子によって支配された」死だ。
人間の身体の「細胞」は数ヶ月ごとに、あるいは毎日もしくは何時間かごとに「入れ替わっている」、とか言われることがある。上記の「心筋」細胞、「神経」細胞以外の全ての細胞にこれは当てはまる。血管を構成する細胞の一つである「赤血球」についても、肝臓の「肝細胞」についても言える。きりがない。
アポトーシスは、「細胞がさまざまな情報をみずから総合的に判断して、遺伝子の発現にもとづいて自死装置を発動する」ことで起きる(下掲書)。
役割を果たし終えた細胞、異常になった細胞が「自死」し、生命体に不要または有害な細胞が除去される。これは生命体たる個体の維持にとって重要だ。
なお、「細胞の死」がつねに個体にとって好ましいわけでは勿論ない。個体の維持に必要不可欠の細胞群が<外界からの襲撃>によって死んでしまえば、「個体の死」に直接につながる。また、「外界」からの影響を無視するとしても、個別の細胞が<分裂>して「細胞の死」が発生する回数には限界がある、とされている。その限界に達してくると、個体の<老化>が顕著になり、「個体の死」と密接に関係する「非再生系細胞」の機能の低下にもつながってくる。「再生系〜」と「非再生系〜」が無関係であるはずはないからだ。
--------
実際には「ふつうの」または正常な「細胞の死」だけが生じているのではない。同じことだが、細胞の全ての「増殖」等が正常に行われているわけではない。
ついでに記しておくが、①細胞が「自死」しないで異常に増える場合—癌(悪性リンパ腫も)、ウイルス感染等、②細胞が異常に「自死」しすぎる場合—エイズ、神経変性疾患(アルツハイマー病等)、虚血性疾患(心筋梗塞、脳梗塞等)等。
ここに見られるように、「心筋」細胞等は<再生>しない「非再生系細胞」だが、「自死」=アポトーシスはありうる。「脳梗塞」による細胞減少=一部または特定部位の「細胞の死」は、いわゆる<後遺症>を生じさせることもある。
--------
「生殖細胞」は「再生系細胞」に含まれる。そして、異常なそれは、早い段階で除去される(=「自死」を余儀なくされる)。受精卵、初期胚も「生殖細胞」の一種だ。
--------
「脳死」を別とすると、人間・個体の「死」の判断基準は、①心臓の拍動の停止、②肺の呼吸の停止、③瞳孔反射の不存在、の三つを充たすこととされてきた。
この③が「神経細胞」の機能停止を少なくとも含んでいるとすると、①が「心筋細胞」、③が「神経細胞」の機能停止を意味している。そして、この二種の細胞はともに「非再生系細胞」であることはじつに興味深いことだ。
これら(一部を含む)も、「再生系細胞」と同様の「死に方」をすることがある。しかし、興味深くかつ重要なのは、これらの「非再生系細胞」は個体自体の「死」と密接に関係している、とされることだ。
--------
<君たちはどう生きるか>と問うてもよいが、<私たちはなぜ死ぬのか>と問うてもよい。
ヒトははるか昔から、自分たちは永遠には生きられない、必ず「死ぬ」と、理屈はわからないままで、<経験的に>知ってきたに違いない。
ヒト・人間には、「寿命」がある。なぜか。
これは、ヒトという生物「種」がそのようなものとして生まれてきた、またはそのようなものとして「進化」してきた、と理解するほかないだろう。
「細胞の死」と同じく、「個体の死」もまた、 「プログラム化された」死であり、「遺伝子によって支配された」死だと考えられる。
もちろん、「種」として把握した場合のことであって、個々の人間の「寿命」・いつ死ぬかが、あらかじめ当該の人の「遺伝子」によって決定されている、という意味ではない。個別の個体次元では、「遺伝子」のほかに、生涯全体で受けてきた「環境」要因を無視することができない(長生きしようという「意欲」または「努力」が全くの無駄でもあるまい)。
しかし、150歳、140歳、130歳まで生きた、という例を、(少なくとも秋月は)全く聞いたことがない。これはいったいなぜなのだろうか。高齢化社会となり、平均寿命も平均余命も長くなっていけば、ヒト・人間は(戦争や自然災害等を無視するとしても)過半以上の者たちが150歳、200歳まで生きるようになる、とは思えない。そうなるためには、よほどの「突然変異」とその「自然選択」化が必要だろう。
「種」として把握した場合のヒト・人間には、 「プログラム化された」死、「遺伝子によって支配された」死が、あらかじめセットされている。これは「思想」・「哲学」、「宗教」・「信仰」の問題ではない。これらは「種」としてのヒトの「死」を考察するに際して、ほとんど何の役にも立たない。
主な参考文献。田沼靖一・遺伝子の夢—死の意味を問う生物学(NH Kブックス、1997)。
——
--------
「細胞」は種々に分類されるのだろうが、つぎの二分が、まずは関心を引く。
第一に、「体細胞」と「生殖細胞」の区別。後者は精子、卵子、初期胚など。
精子・卵子は圧倒的多数の「体細胞」と違って減数分裂により生まれ、23本の「染色体」しかもたない。そんなことよりも、つぎの重要な違いをゲノム編集に関係して、秋月は知った。
すなわち、「体細胞」はゲノム編集の対象にすでになっている。換言すると、〈クリスパ・キャス9〉という「遺伝子」改変・「ゲノム」編集の方法がすでに適用されているのは、「体細胞」だ。一方、「生殖細胞」のゲノム編集については論議があり、大勢的な一致はない。但し、中国人研究者が(アメリカ留学で得た知識・技術を発展させて)中国で初期胚をゲノム編集し、それを女性に移植し、その女性は双子の女の子を出産した「事実」がある、とされる。
前者のゲノム編集の影響・効果は一世代に限定される。致命的疾患を発現させているような「体細胞」内の遺伝子が改変されても、その改変(・ゲノム編集)は次世代に影響を与えない。一方、遺伝子が改変された「生殖細胞」はその子どもの「生殖細胞」(女性だと卵子)に継承される。
--------
第二に、「再生系細胞」と「非再生系細胞」の区別。
前者・「再生系細胞」は、増殖したり、分化したりなどをする。新しい「細胞」に<再生>しうる。
後者・「非再生系細胞」は、増殖・分化しない。ヒトの場合、初期胚・胎児は増殖と分化を繰り返して「成長」するが、母体から離れるとき(新生児となるとき)以降は、心臓を拍動させる「心筋」細胞と脳内の「神経」細胞(ニューロン)は、もはや増殖することがない、とされる。
心筋梗塞や脳梗塞によって「壊死」した「心筋細胞」や「神経細胞」はもはや<再生>することがない。なお、例外は全くない、のではない、とされる。
この区別に表向きは隠されているようでもある重要な意味は、ヒト、つまり人類、人間の「細胞」や個体の「死」ないし「死に方」と密接な関係があることだ。
--------
「再生系細胞」が増殖するとは一つの細胞から二つの、そして四つの、…10回で1024個の同一の細胞が生まれることだ(限界まで増殖はつづく)。かつまた、元の、増殖前の細胞が「死ぬ」ことも意味している。
「分化」の場合も同じ。異なる細胞に「分化」する前の元の細胞は「死ぬ」。
上で「増殖したり、分化したりなどをする」と「など」を挿入したのは「死ぬ」こともあるからだ。
ここで「死」という言葉、概念を使うのは紛らわしいかもしれない。あくまでも「細胞の死」であって、通常は「死」の意味で用いられているだろう「個体の死」ではないからだ。その意味では、「消滅」の方がよいだろうか。だが、生命体の基本的単位である「細胞」についても「死」を語って奇妙ではないし、逆に、「個体の死」もまた、「個体の消滅」だ。
「細胞の死」またはその仕組みのことを<アポトーシス>と言うことがある(下掲書によると1972年に初めて提唱された)。
そして、この現象または仕組みはヒトを含む多細胞生物にもともと内在しているものとされる。「プログラム化された」死であり、「遺伝子によって支配された」死だ。
人間の身体の「細胞」は数ヶ月ごとに、あるいは毎日もしくは何時間かごとに「入れ替わっている」、とか言われることがある。上記の「心筋」細胞、「神経」細胞以外の全ての細胞にこれは当てはまる。血管を構成する細胞の一つである「赤血球」についても、肝臓の「肝細胞」についても言える。きりがない。
アポトーシスは、「細胞がさまざまな情報をみずから総合的に判断して、遺伝子の発現にもとづいて自死装置を発動する」ことで起きる(下掲書)。
役割を果たし終えた細胞、異常になった細胞が「自死」し、生命体に不要または有害な細胞が除去される。これは生命体たる個体の維持にとって重要だ。
なお、「細胞の死」がつねに個体にとって好ましいわけでは勿論ない。個体の維持に必要不可欠の細胞群が<外界からの襲撃>によって死んでしまえば、「個体の死」に直接につながる。また、「外界」からの影響を無視するとしても、個別の細胞が<分裂>して「細胞の死」が発生する回数には限界がある、とされている。その限界に達してくると、個体の<老化>が顕著になり、「個体の死」と密接に関係する「非再生系細胞」の機能の低下にもつながってくる。「再生系〜」と「非再生系〜」が無関係であるはずはないからだ。
--------
実際には「ふつうの」または正常な「細胞の死」だけが生じているのではない。同じことだが、細胞の全ての「増殖」等が正常に行われているわけではない。
ついでに記しておくが、①細胞が「自死」しないで異常に増える場合—癌(悪性リンパ腫も)、ウイルス感染等、②細胞が異常に「自死」しすぎる場合—エイズ、神経変性疾患(アルツハイマー病等)、虚血性疾患(心筋梗塞、脳梗塞等)等。
ここに見られるように、「心筋」細胞等は<再生>しない「非再生系細胞」だが、「自死」=アポトーシスはありうる。「脳梗塞」による細胞減少=一部または特定部位の「細胞の死」は、いわゆる<後遺症>を生じさせることもある。
--------
「生殖細胞」は「再生系細胞」に含まれる。そして、異常なそれは、早い段階で除去される(=「自死」を余儀なくされる)。受精卵、初期胚も「生殖細胞」の一種だ。
--------
「脳死」を別とすると、人間・個体の「死」の判断基準は、①心臓の拍動の停止、②肺の呼吸の停止、③瞳孔反射の不存在、の三つを充たすこととされてきた。
この③が「神経細胞」の機能停止を少なくとも含んでいるとすると、①が「心筋細胞」、③が「神経細胞」の機能停止を意味している。そして、この二種の細胞はともに「非再生系細胞」であることはじつに興味深いことだ。
これら(一部を含む)も、「再生系細胞」と同様の「死に方」をすることがある。しかし、興味深くかつ重要なのは、これらの「非再生系細胞」は個体自体の「死」と密接に関係している、とされることだ。
--------
<君たちはどう生きるか>と問うてもよいが、<私たちはなぜ死ぬのか>と問うてもよい。
ヒトははるか昔から、自分たちは永遠には生きられない、必ず「死ぬ」と、理屈はわからないままで、<経験的に>知ってきたに違いない。
ヒト・人間には、「寿命」がある。なぜか。
これは、ヒトという生物「種」がそのようなものとして生まれてきた、またはそのようなものとして「進化」してきた、と理解するほかないだろう。
「細胞の死」と同じく、「個体の死」もまた、 「プログラム化された」死であり、「遺伝子によって支配された」死だと考えられる。
もちろん、「種」として把握した場合のことであって、個々の人間の「寿命」・いつ死ぬかが、あらかじめ当該の人の「遺伝子」によって決定されている、という意味ではない。個別の個体次元では、「遺伝子」のほかに、生涯全体で受けてきた「環境」要因を無視することができない(長生きしようという「意欲」または「努力」が全くの無駄でもあるまい)。
しかし、150歳、140歳、130歳まで生きた、という例を、(少なくとも秋月は)全く聞いたことがない。これはいったいなぜなのだろうか。高齢化社会となり、平均寿命も平均余命も長くなっていけば、ヒト・人間は(戦争や自然災害等を無視するとしても)過半以上の者たちが150歳、200歳まで生きるようになる、とは思えない。そうなるためには、よほどの「突然変異」とその「自然選択」化が必要だろう。
「種」として把握した場合のヒト・人間には、 「プログラム化された」死、「遺伝子によって支配された」死が、あらかじめセットされている。これは「思想」・「哲学」、「宗教」・「信仰」の問題ではない。これらは「種」としてのヒトの「死」を考察するに際して、ほとんど何の役にも立たない。
主な参考文献。田沼靖一・遺伝子の夢—死の意味を問う生物学(NH Kブックス、1997)。
——